 全国の士業の方はもちろん、あらゆる専門分野をお持ちの方からの相互リンクを随時受付中です! 全国の士業の方はもちろん、あらゆる専門分野をお持ちの方からの相互リンクを随時受付中です!
 詳細はこちら 詳細はこちら |
|
 |
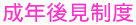 |
|
成年後見制度とは 判断能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害のある方)が損害や被害を受けないように権利を保護する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、さらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより本人を保護・支援します。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることにより,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
◆ 法定後見制度の3類型
① 後見
精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者、つまり全面的にバックアップが必要な方ということになります。
法定後見人として後見人が本人をサポートします。
② 保佐
精神上の障害によって,判断能力が著しく不十分な者が該当します。つまり他人にそそのかされて、自分に不利益な契約を結んでしまう可能性が高い方ということになります。
法定後見人として保佐人が本人をサポートします。
③ 補助
精神上の障害によって,判断能力が不十分な者が該当します。つまり判断能力が不十分ながらもご自分で契約等ができるかもしれないが、適切に判断できるかどうか心配があるため、第三者に手伝ってもらったり、代理してもらう方がよい方ということになります。
法定後見人として補助人が本人をサポートします。
★法定後見制度の利用を希望するときは、本人の住所地の裁判所に審判を申し立てます。
◆ 申立てできる人
■ 本人,配偶者,四親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,検察官 (任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます)
■ 市町村長(身寄りのない場合)
◆ 申立てに必要なもの
■ 申立書1通
■ 収入印紙
■ 登記印紙
■ 郵便切手
■ 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
■ 本人の戸籍謄本,戸籍附票,登記事項証明書,診断書各1通
■ 成年後見人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,登記事項証明書各1通
◆ 申し立て後の流れ
家裁による調査 ⇒ 専門医による鑑定 ⇒ 家裁による尋問 ⇒ 審判決定 ⇒ 法定後見開始
★ 原則として「保佐」「後見」を申立てた場合、家庭裁判所は本人の判断能力や障害の程度がどれぐらいか判断するために、医師に鑑定を依頼します。鑑定には10万円前後の費用がかかります。
★ 申立から審判決定までは平均2〜5ヶ月かかります。
★ 法定後見人に支払う費用(報酬)は、サポートの内容と本人の支払い能力などに応じて家庭裁判 所が決めます。
◆ 成年後見人の資格
特に法律上の制限はありません。
親族の他、弁護士、行政書士、社会福祉士などの専門家や法人格を有する福祉団体等も選任する ことができます。また、複数の後見人を選任することも可能です。
また、家庭裁判所が必要だと判断した場合、後見人の他に監督人が選任されることがあります。
◆ 成年後見の登記
後見開始の審判がなされると、家庭裁判所書記官の嘱託によって成年後見の登記が行われます。※戸籍には記載されることはありません。
成年後見の登記は東京法務局で全国の成年後見登記事務を取り扱っています。
登記が完了すると請求により、その内容を証明する『登記事項証明書』が発行されます。
『登記事項証明書』の交付を請求できる人は、本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人など一定の方に限定されています。
なお、登記されていないことの証明書とは,後見登記等ファイルに記載されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
◆任意後見契約
任意後見制度を利用するには、予め任意後見契約を結んでおく必要があります。
任意後見契約は公証役場で公正証書の形で結ばなければなりません。
まず、誰に任意後見人になってもらいたいかを決めます。
任意後見人には親族の方はもちろん、弁護士、行政書士などの第三者がなることが出来ます。
その後、どんなサポートをお願いしたいかを本人とそのサポートを依頼された人が話し合い任意後見の内容を決めます。これが任意後見契約となります。
将来、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見受任者は任意後見人として契約した内容についてサポートをおこないます。
◆ 任意後見監督人の職務
①任意後見人の事務を監督すること。
②任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
③急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
④任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。 と定められています。
さらに任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができるとなっており、任意後見人の権利濫用を防止する仕組みとなっています。
◆任意後見制度の開始
本人の判断能力が不十分になったとき、任意後見契約を開始するための手続きが必要となります。本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行います。
◆ 申立てできる人
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
◆ 申立てに必要なもの
■ 申立書1通
■ 収入印紙
■ 登記印紙
■ 郵便切手
■ 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
■ 本人の戸籍謄本,戸籍附票,登記事項証明書,診断書各1通
■ 任意後見人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,登記事項証明書各1通
◆ 後見人の報酬
後見人の報酬については契約内容等によりますが、弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合は月額3万円前後が基準となります。親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようです。
後見監督人の報酬は本人の財産等を考慮して家庭裁判所が決定します。
|